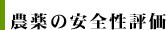 |
|
| それでは、意図的に細菌や害虫を殺したり、雑草を駆除したりする目的で使用される農薬のリスクはどれほどであろうか。恐らく、一般的な市民の印象は「農薬と聞くと何となく不安である」といったところであり、少なからず「それなりのリスクはある」と感じておられることであろう。もちろん、それはそれで必ずしも誤った認識ではない。しかし、農薬取締法に基づいて新規の農薬を登録する際には、医薬品以上に厳しい毒性試験を実施してそれらのデータを提出しなければならないことや、その安全性に関して内閣府の食品安全委員会を始めとする様々な国家機関による厳格な審査を受けていることは、意外に知られていない。参考のため、食用作物に適応される農薬に課せられる主な毒性試験の種類を、表1に示す。 |
|
| 表1. 農薬のヒトに対する安全性を担保するための主な毒性試験 |
|
農薬使用時の安全性評価
(農業従事者の安全確保) |
残留農薬の安全性評価
(消費者の安全確保) |
急性毒性
(経口毒性、経皮毒性、吸入毒性、眼刺激性、皮膚感作性など) |
急性毒性(経口毒性、経皮毒性) |
| 亜急性毒性(経口毒性、吸入毒性など) |
亜急性毒性(経口毒性) |
| 特殊毒性(催奇形性、変異原性) |
長期毒性(慢性毒性、発がん性) |
| その他(生体の機能に及ぼす影響) |
特殊毒性(繁殖毒性、催奇形性、変異原性) |
|
その他(生体内運命、生体の機能に及ぼす影響) |
|
|
農薬の毒性試験は、使用時安全を確保するための試験と、消費者安全を確保するための試験に大別される。例えば、農作業時には比較的高濃度の農薬に直接接触したり、噴霧した農薬を吸入したりするリスクがあるため、農業従事者の安全を確保するための試験では様々な曝露経路による高濃度で短期の曝露に対する毒性が細かく調べられる。また、農作業に従事する方々の中には妊婦も含まれる可能性があるため、胎児に対する影響を調べる催奇形性試験も実施される。一方、都市部に住むごく普通の市民が直接農作業に携わることはまれなため、一般に消費者が高濃度の農薬に曝露される事象は考え難い。しかし、これらの人々も毎日の食事を介して比較的低濃度の農薬に長期間晒される可能性があるので、消費者の安全を担保するためには、主として経口曝露経路による慢性毒性や発がん性あるいは繁殖毒性の有無を中心に評価する必要が生ずる。
これらの毒性試験に用いられる実験動物の種類を、表2に示す。 |
|
|
表2. 農薬の毒性試験に用いられる実験動物の種類
|
|
| 実験動物の種類 |
毒性試験 |
| ラットおよびマウス |
急性毒性試験、亜急性毒性試験、慢性毒性試験、発がん性試験、
繁殖毒性試験、催奇形性試験、神経毒性試験、遺伝毒性試験、免疫毒性試験など |
| モルモット |
皮膚感作性試験など |
| ウサギ |
眼刺激性試験、催奇形性試験など |
| イヌ |
亜急性毒性試験、慢性毒性試験など |
| ニワトリ |
遅発性神経毒性試験など |
|
|
| 表から明らかなように、毒性試験ではラットやマウスが汎用される。しかし、動物の種によっては、特異的な反応が起こったり逆に極めて反応が鈍かったりする可能性があるので、重要な試験については複数の動物を用いて同一の試験を実施する。 |
|