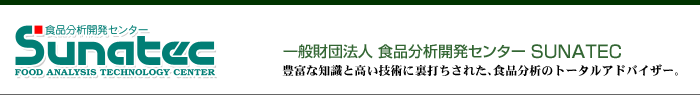|
たんぱく質の検査方法 -ケルダール法-
一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC
第一理化学検査室 たんぱく質とはたんぱく質は、人の体の様々な部分を作るのに欠かせない栄養素であり、動物性たんぱく質(肉類、魚介類、卵、乳製品)と植物性たんぱく質(豆類、穀類)の2つに分類される。主として、アミノ酸からできており、アミノ酸の数は20種類ある。また、その中には体内で合成できないアミノ酸が9種類存在する。それらは、必須アミノ酸とよばれ、食事から摂取することが必要である。 分析方法たんぱく質の分析方法は、新たに施行された「食品表示基準について(平成27年3月30日付け 消食表第139号)」においても窒素定量換算法が採用されている。その中で、これまでの「栄養表示基準における栄養成分等の分析方法等について(平成11年4月26日付け 衛新第13号)」においては、ケルダール法のみが採用されていたが、食品表示基準においては、ケルダール法だけでなく新たに燃焼法も採用された。 ケルダール法の概要含窒素有機物を分解促進剤の存在下において硫酸で分解して、窒素をアンモニアに変換する(分解)。次いで、水酸化ナトリウムを加えてアルカリ性として、遊離したアンモニアを水蒸気蒸留してホウ酸溶液に捕集する(蒸留)。得られたアンモニア捕集液を硫酸標準溶液で滴定して窒素量を求める(滴定)。 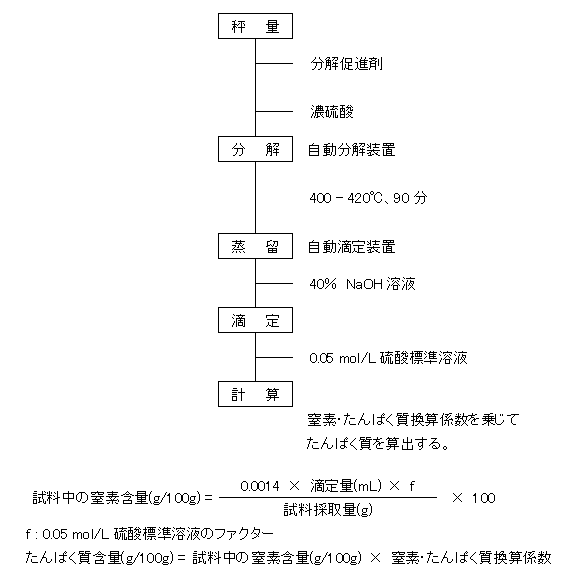 図1.ケルダール法の検査フロー
上記食品以外については、通常6.25を用いる。 分析方法の留意点と対応たんぱく質の分析方法は、先にも述べたように窒素定量換算法であり、全窒素を定量し、窒素・たんぱく質換算係数を乗じて評価する。しかしながら、食品中の窒素化合物は必ずしもたんぱく質のみではない。食品によってはアミノ酸類、アミド類、プリン塩基類及びクレアチン類等を多く含有することもある。そのため、たんぱく質以外の窒素化合物を豊富に含む食品にあっては、たんぱく質が過大評価されてしまう点に留意すべきである。 参考文献1)食品表示基準について(平成27年3月30日付け 消食表第139号) サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |