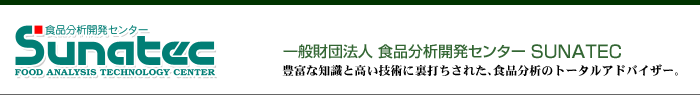|
長期流行を繰り返すノロウイルス遺伝子型GII.4の特徴と変遷
広島文教女子大学 人間科学部 人間栄養学科
福田 伸治 はじめにノロウイルスは5つの遺伝子グループに分けられ,そのうち遺伝子グループI,IIおよびIVがヒトに感染するが,グループIVによる感染症の発生は少なく,グループIIが主流である。さらに,グループIおよびIIには多くの遺伝子型が存在する。過去には遺伝子型GII.5やGII.12の流行が多く見られたが,2003年以降から遺伝子型GII.4が増加し始め,今では遺伝子型GII.4が主流となっている。この傾向は世界的にも同様である。
1. 食品媒介感染症における遺伝子型の変遷(広島県を例として)1, 2)2000/01年から2009/10年シーズンの概要を表1に示した。大部分が遺伝子グループIIにより発生しており,遺伝子グループIの関与は小さいことが分かる。遺伝子グループIIの中では流行シーズンにより多少の差異が見られるが,2004/05年シーズン以降は遺伝子型GII.4がノロウイルス集団発生に大きく関与していることが確認される。その他,遺伝子型GII.4以外にも次のような特徴がみられる。遺伝子型GII.5を原因とする集団発生は2003/04年シーズン以降は認められていない。また,遺伝子型GII.3を原因とする集団発生は流行したシーズンの翌シーズンの発生はなく,2003/04年シーズン以降では隔年での発生で,連続した流行が認められていない。 表1 2000/01年から2009/10年シーズンにおける遺伝子型の変遷(PDF:28KB)
2. 感染性胃腸炎の爆発的な流行わが国における感染性胃腸炎の大流行は,前述のごとく2006/07年シーズンおよび2012/13年シーズンに見られる。2012/13年シーズンは2006/07年シーズンに及ばないものの,第42週頃から患者数の早い立ち上がりが見られ,他のシーズンと比較し約2週間早くピークに達している(図1)。この流行はノロウイルスが主体で,しかも遺伝子型GII.4がその大部分を占めている。大流行した2006/07年シーズン以降4シーズンにわたり,2006/07年シーズンに流行した遺伝子型GII.4亜株(遺伝子型でみると同じGII.4に分類されるが,遺伝子配列に変異が見られる)が優勢であったものの,その後減少傾向を示し,年々新しい遺伝子型GII.4亜株の出現がみられる。
3. 遺伝子型GII.4を原因とする集団発生事例の発症率3)全国で発生したノロウイルス集団発生事例の発症率を解析した報告をみると,遺伝子型GII.3を原因とする集団発生事例の発症率は他の遺伝子型に比べ高いが,遺伝子型GII.4を原因とする集団発生事例の発症率は他の遺伝子型に比べ低い傾向が観察されている(図2)。しかしながら,無症状者(不顕性感染者)も患者に匹敵する多量のウイルスを糞便中に排泄しており4),無症状者は本人が気付かないうちに感染を拡大させている可能性があることが指摘されている。 図2 遺伝子型GII.4の発症率(箱ひげ図)(PDF:65KB)
4. 糞便中に排泄されるウイルス量5)定量PCR法(リアルタイムPCR法)により,患者糞便中に排泄されるウイルス遺伝子量を測定した結果を図3に示す。多量のウイルスが糞便中に排泄されていることが認められる。遺伝子グループ別比較では,遺伝子グループIIは遺伝子グループIに比べ排泄量が多い傾向にあることが認められる。また,遺伝子グループIIの内では,遺伝子型GII.4の糞便中への排出量は約109コピー/g糞便(中央値)で,他の遺伝子型に比べウイルス排泄量が若干多い傾向が認められている。この傾向は,他国においても同様である6)。 図3 糞便中に排泄されるウイルス量の比較(PDF:73KB)
5. 糞便中への排泄期間7)遺伝子型GII.4についての排泄期間を観察した例では,症状消失後も糞便中にウイルス遺伝子が排泄されていることが確認されている。症状消失後も長期間にわたり排泄されていることは,新たな感染源になり得る可能性を持つことになる。なお,小児が成人に比べると排泄期間が長い傾向にある。
6. ゲノムの組み換え(キメラウイルスの出現)ノロウイルスのゲノム(核酸)は,1本鎖プラス鎖RNA(約7.5kb)で,3つのオープンリーディングフレーム(タンパク質コード領域;OFR1,ORF2,ORF3)から成る(図4)。ノロウイルスにはORF1とORF2のジャンクション部分を境に遺伝子グループ内でゲノムを組み換えたキメラウイルス8)(例えばOFR1/ORF2ジャンクションの前半部分の遺伝子型がGII.4で,後半部分の遺伝子型がGII.2)が多数報告されているが,長期に流行を繰り返す遺伝子型GII.4には特徴的な点がある。大流行した2006/07年シーズンおよび2012/13年シーズンとも,OFR1/ORF2ジャンクションの前半部分のポリメラーゼ領域も後半部分のカプシド領域も遺伝子型では同じGII.4に分類されるが,詳細に観察すると,遺伝子情報の異なる遺伝子型GII.4亜株間で遺伝子組換えを行ったキメラウイルスが出現し,それが大流行の大きな原因であったことが報告されている9,10)。
7. カプシド領域(VP1)における変異OFR2はウイルスの構造タンパク質(ゲノムを包むタンパク質の殻)をコードしている部分であり,P1およびP2ドメインと呼ばれるウイルスの外側に位置する部分が含まれる(図4)。集団発生事例などのノロウイルス感染症の原因の主体を占める遺伝子型GII.4をみると,P1およびP2ドメインにアミノ酸変異(アミノ酸置換)が集中し,経年的変化が認められる1,11)。これにより抗原性が変化し,これまでに獲得した抗体が働かなくなることが推察されている。特に,VP1の296-298番目,393-395番目および412-414番目のアミノ酸の経年変化が容易に観察できる部位(Variant Specific Epitope)1,12,13)であると考えられる(図5)。これらの部分はP2ドメインで,ウイルス粒子の最外郭に相応する部分に位置する。その他,Sドメインの6番目,9番目,15番目および45番目のアミノ酸にも有意な変異が認められる14-17)。このSドメインはVP1のアセンブリーに関与する部分である。 図5 P2ドメインにおけるVariant Specific Epitope(PDF:133KB)
まとめノロウイルスは未だに人工培養法が確立されていないウイルスであるため,その検出には遺伝子学的手法(PCR法,LAMP法など)が主流となっているが,ゲノムサイズが小さいことから,種々の方面から遺伝子系統解析が精力的に行われてきた。食中毒などのノロウイルス感染症の原因となる遺伝子型には経年的変遷が認められ,以前には多かった遺伝子型GII.5やGII.12が近年では少なくなっている。しかしながら,2003/04年シーズンあるいは2004/05年シーズン頃から遺伝子型GII.4は増加するなど,流行する遺伝子型が変化しながら継続したノロウイルス感染症の発生を繰り返しているが,なぜか遺伝子型GII.4は長期にわたる流行を今も繰り返している。これは,遺伝子型GII.4がウイルス粒子の最も外側に位置するP2ドメインを中心にアミノ酸変異を繰り返すことにより,あるいは遺伝子型GII.4亜株間で遺伝子組み換え(キメラウイルス)を行うことにより抗原変異が起こり,集団免疫から逃れているのではないかと推定される18-20)。このように,遺伝子変化が遺伝子型GII.4の流行継続に関係しているようであるが,まだまだ不明な点も多い。これに加えて,遺伝子型GII.4は発症率が低いのにもかかわらず,糞便中に排泄されるウイルス量が多く,無症状のウイルス保有者(不顕性感染者)が広範囲にウイルスを拡散させていること,症状消失後も糞便中に長期間ウイルスが排泄されていることも確認されており,継続した流行の1つの要因になり得るのかもしれない。明確な数値は存在しないものの,10-100個程度で感染が成立すると言われている21)。
文献1)Fukuda S, Takao S, Shigemoto N, Tanizawa Y, Semo M (2010): Transition of genotypes associated with norovirus gastroenteritis outbreaks in a limited area of Japan, Hiroshima Prefecture, during eight epidemic seasons. Arch Virol 155, 112-115.
略歴福田伸治(ふくだ しんじ) 博士(医学) 1978年 日本大学農獣医学部獣医学科卒業 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
||
| Copyright (C)Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |