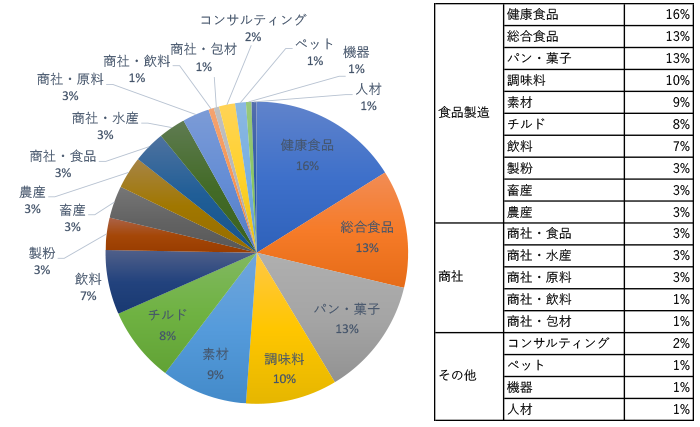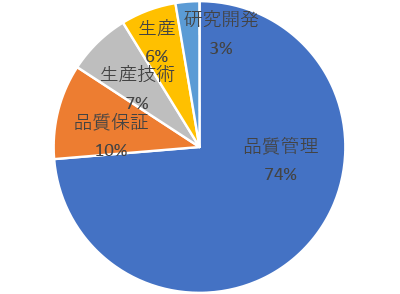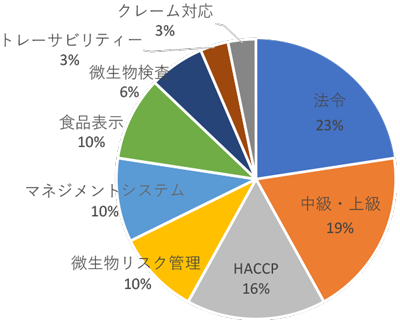働き方の多様化が進む中、食品企業の品質管理部門における人材育成は企業競争力の要となっている。今回、当財団が2023年度に開講した資格検定「食品品質管理士」に関するアンケートやインタビュー調査を実施した結果から、企業における職場学習の一つとして、この資格検定を導入することの効果と今後の課題を整理した。
近年の動向として、ワークライフバランスの重視や自己実現・成長機会の追求といった働き方の多様化、価値観の変化が進行している。また、終身雇用制度や職能資格制度などの雇用政策の転換により、従来のOJTやOFF-JTといった人材開発施策の実施は減少傾向にあるが、その一方で、企業の競争優位性を確保するため、人材育成の重要性はこれまで以上に高まっている。このような状況下において、食品企業の品質管理部門は消費者の安全と健康を守り、企業の信頼を維持するための最重要機能の一つであると同時に、その人材の育成・教育は企業の競争優位性を確立する上で極めて重要な要素となっている。より具体的な例をあげると、食品安全マネジメントシステムの実践的な運用、品質トラブルの未然防止、トラブル発生時の迅速かつ適切な対応ができる人材の育成が求められている。そこで当財団では、このような食品企業における品質管理教育を支援するため、公益目的事業の一環として「食品品質管理士」の資格検定を開講しており、このたび、食品品質管理士の受講者へのアンケートおよびインタビュー調査を実施し、その分析結果をもとに、食品の品質管理における今後の職場学習の方向性と課題を以下に整理しました。本内容が皆様の人材育成活動の一助となれば幸いです。