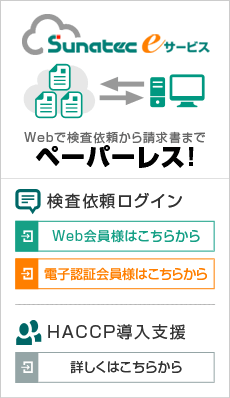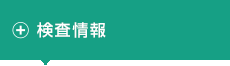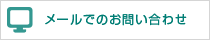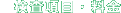食品分析開発センターSUNATEC > 技術情報 >ビタミン・ミネラル・アミノ酸・機能性成分
ビタミンとは
ビタミンとは「微量で体内の代謝に重要な働きをしているにもかかわらず、自分でつくることができない化合物」と定義されている栄養成分です。定義の通り、ビタミンを摂取するためには、各種ビタミンを含む食品を食べる必要があります。
ビタミンには油溶性ビタミンと水溶性ビタミンがあり、現在13種類が確認されています。また各種ビタミンは、単一の成分では無く、その機能から分類されている名称です。つまり、同じ機能をもつ成分であれば、同じビタミンとして分類されます。 例えばビタミンAは、レチノールやα-カロテン、β-カロテン等がビタミンAとして分類されているように、複数の異なる成分が同じビタミンとして分類されています。 そのため、各ビタミンの量を調べるには、そのビタミンとして分類されている各成分量まで調べる必要があります。
ビタミンには油溶性ビタミンと水溶性ビタミンがあり、現在13種類が確認されています。また各種ビタミンは、単一の成分では無く、その機能から分類されている名称です。つまり、同じ機能をもつ成分であれば、同じビタミンとして分類されます。 例えばビタミンAは、レチノールやα-カロテン、β-カロテン等がビタミンAとして分類されているように、複数の異なる成分が同じビタミンとして分類されています。 そのため、各ビタミンの量を調べるには、そのビタミンとして分類されている各成分量まで調べる必要があります。
検査の目的
 食品表示基準に沿った適切な表示を行うための資料として、また添加量の確認、製造工程中での減衰量の調査等についても、実際の製品での確認が有効です。
食品表示基準に沿った適切な表示を行うための資料として、また添加量の確認、製造工程中での減衰量の調査等についても、実際の製品での確認が有効です。栄養機能食品においては規格基準内の含有量かを確認するため、検査お薦めします。
 体内のミネラル量はわずかですが、人体を構成する各種成分又は素材となったり、生命活動に欠くことのできない代謝調節作用などの多くの生理作用と密接な関係をもっています。ミネラルは炭水化物、脂質及びタンパク質とともに、私たちの体をつくる重要な栄養素となっています。栄養関連制度の中では、平成16年3月の健康増進法改正に伴い「栄養機能食品」及び「栄養成分の補給ができる旨の表示」の対象となる栄養成分に亜鉛、銅及びマグネシウムの3成分が追加されています。
体内のミネラル量はわずかですが、人体を構成する各種成分又は素材となったり、生命活動に欠くことのできない代謝調節作用などの多くの生理作用と密接な関係をもっています。ミネラルは炭水化物、脂質及びタンパク質とともに、私たちの体をつくる重要な栄養素となっています。栄養関連制度の中では、平成16年3月の健康増進法改正に伴い「栄養機能食品」及び「栄養成分の補給ができる旨の表示」の対象となる栄養成分に亜鉛、銅及びマグネシウムの3成分が追加されています。検査の目的
カルシウムや亜鉛などのミネラルを強調表示する場合に、基準値を満たしているかどうかの確認。
加工食品において、食塩相当量 (ナトリウム) の適切な表示を行うため。
アミノ酸とは
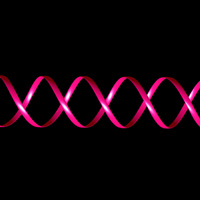 アミノ酸とは、一般的には「たんぱく質」を構成している成分のことを指します。「グルタミン酸」や「アスパラギン酸」といった名称が良く知られています。
アミノ酸は数百種類以上も発見されていますが、たんぱく質を構成しているアミノ酸は、20種類です。私たちが肉や魚などを食べると、その中に含まれるたんぱく質は、この20種類に分解され、栄養素として吸収されます。吸収されたアミノ酸は、エネルギー源や、私たちの体をつくるたんぱく質として再構成されます。
このように、アミノ酸は生命活動に必須の非常に重要な物質です。
アミノ酸とは、一般的には「たんぱく質」を構成している成分のことを指します。「グルタミン酸」や「アスパラギン酸」といった名称が良く知られています。
アミノ酸は数百種類以上も発見されていますが、たんぱく質を構成しているアミノ酸は、20種類です。私たちが肉や魚などを食べると、その中に含まれるたんぱく質は、この20種類に分解され、栄養素として吸収されます。吸収されたアミノ酸は、エネルギー源や、私たちの体をつくるたんぱく質として再構成されます。
このように、アミノ酸は生命活動に必須の非常に重要な物質です。検査の目的
 たんぱく質中の各アミノ酸量の調査や、アミノ酸スコアの確認を行う場合、構成成分は食品によってもことなります。また、時期や生育場所、品種等によっても変わることがありますので、実際の食品を対象とした加水分解アミノ酸の検査結果による評価をお薦めします。
また食品の呈味性の違いに対するアミノ酸の影響を調べる場合、遊離アミノ酸の検査による評価をお薦めします。
たんぱく質中の各アミノ酸量の調査や、アミノ酸スコアの確認を行う場合、構成成分は食品によってもことなります。また、時期や生育場所、品種等によっても変わることがありますので、実際の食品を対象とした加水分解アミノ酸の検査結果による評価をお薦めします。
また食品の呈味性の違いに対するアミノ酸の影響を調べる場合、遊離アミノ酸の検査による評価をお薦めします。アミノ酸━加水分解と遊離の違い
アミノ酸は様々な機能を持つ栄養成分です。その一つがアミノ酸の呈味性です。アミノ酸には特有の味があることが知られ、また一つのアミノ酸から複数の異なる5基本味(甘味、酸味、苦味、塩味、うま味)を示す成分も多くあります。
これらの呈味性を示すアミノ酸は、食品の中では「遊離」の状態で存在するアミノ酸であり、たんぱく質を構成しているアミノ酸とは別に、単独で存在しているアミノ酸です。
栄養成分として、またたんぱく質の構成成分としてのアミノ酸量を調べる場合には、たんぱく質をアミノ酸の状態まで加水分解し、その量を調べます。それに対し、呈味性を調べる場合には、遊離の状態で存在するアミノ酸のみの量を調べます。
これらの呈味性を示すアミノ酸は、食品の中では「遊離」の状態で存在するアミノ酸であり、たんぱく質を構成しているアミノ酸とは別に、単独で存在しているアミノ酸です。
栄養成分として、またたんぱく質の構成成分としてのアミノ酸量を調べる場合には、たんぱく質をアミノ酸の状態まで加水分解し、その量を調べます。それに対し、呈味性を調べる場合には、遊離の状態で存在するアミノ酸のみの量を調べます。
機能性成分とは
機能性成分とは、一般に生命活動に必須の栄養素では無いものの、健康を維持したり、抗酸化性を示す、発がん性物質等の有害物質の作用を緩和する。等の様々な機能的効果が期待される成分です。
良く知られている成分には、温州みかんの「β-クリプトキサンチン」や、お茶の「カテキン」、大豆の「イソフラボン」、アミノ酸のひとつである「γ-アミノ酪酸(GABA)」等があります。
良く知られている成分には、温州みかんの「β-クリプトキサンチン」や、お茶の「カテキン」、大豆の「イソフラボン」、アミノ酸のひとつである「γ-アミノ酪酸(GABA)」等があります。
検査の目的
 各種機能性成分の定量分析、定性分析。
各種機能性成分の定量分析、定性分析。 機能的効果が報告されている有効成分の含有量の調査。
機能性成分の含有量の調査、機能的効果が期待される物質の研究のためのデータ収集。
新しい効果をもつ物質の確認や評価。
機能性成分の検査
機能性成分は、特定の野菜、果実等に多く含まれる成分であることも多く、検査方法も特定の食品に対して適用される方法であることが多くあります。
食品全般を対象として汎用的に用いられている検査方法は少ないことから、対象となる食品で検査可能かを確認する必要があります。
機能性成分の種類
代表的な機能性成分と、それを含む食品の例を以下の一覧に示します。
|